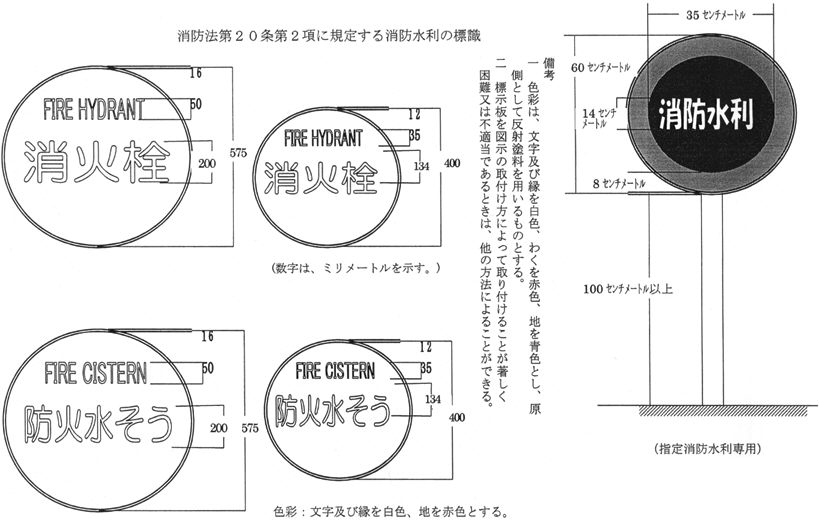
|
���z���̍���
|
�ۗL����
|
|
30���[�g������
|
3���[�g���ȏ�15���[�g������
|
|
30���[�g���ȏ�33���[�g������
|
3���[�g���ȏ�13���[�g������
|
|
33���[�g���ȏ�
|
4���[�g���ȏ�12���[�g������
|
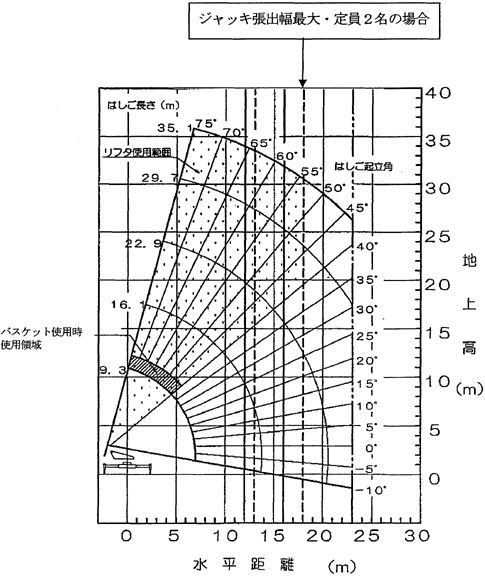
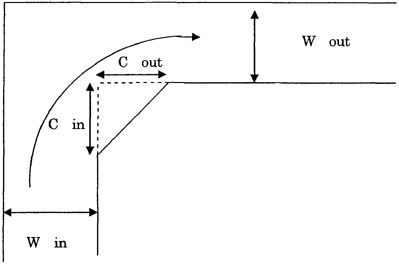
|
���H��(m)
|
���ݐ�(m)
|
||
|
�i���H
W�@in
|
�ޏo�H
W�@out
|
�i���H
C�@in
|
�ޏo�H
C�@out
|
|
4
|
4
|
4.5
|
9.7
|
|
5
|
3.8
|
5.7
|
|
|
6
|
2.6
|
2.6
|
|
|
7
|
1.7
|
1.5
|
|
|
8
|
0.2
|
0.8
|
|
|
9
|
0
|
0
|
|
|
5
|
4
|
3.4
|
8.6
|
|
5
|
1.5
|
4.8
|
|
|
6
|
0.4
|
1.7
|
|
|
7
|
0.5
|
0.1
|
|
|
8
|
0
|
0
|
|
|
6
|
4
|
2.7
|
8.8
|
|
5
|
1.9
|
3.8
|
|
|
6
|
0.9
|
0.9
|
|
|
7
|
0
|
0
|
|
|
7
|
4
|
2.4
|
7.8
|
|
5
|
1.5
|
2.5
|
|
|
6
|
0.5
|
0.1
|
|
|
7
|
0
|
0
|
|
(�\)
���h�{���c��
|
�N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l ���c�\���ҁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{���J���s�ד��ɔ������h�{�݂Ɋւ���v�j�Ɋ�Â����L�̂Ƃ��苦�c���܂��B �L |
|||||
|
�{�s���̏ꏊ |
�@ |
||||
|
�J�����Ƃ̊T�v |
�@ |
||||
|
�{�s���̖��� |
�@ |
||||
|
�{�s���̖ʐ� |
m 2 |
�\��p�r |
�@ |
||
|
�����c���e |
�@(�@�@)���h���� �@�@�ݒu�@�@�h�ΐ���(�@�@)t(�@�@)��E(�@�@)t(�@�@)�� �@�@�@�@�@�@�@���ΐ��@(�@�@)mm(�@�@)��E(�@�@)mm(�@�@)�� �@�@�ېݒu�@�k���R�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l �@�@�W���y�ѕW���@�@�@�ݒu�E�ېݒu �@�@�A��(���n�@���ȊǗ�) |
||||
|
�@(�@�@)���h�����p��n �@�@�ݒu�@�@(�@�@)��(�@�@)�ӏ��E(�@�@)��(�@�@)�ӏ� �@�@�ېݒu �@�@�k���R�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l �@�@�W���y�ѕW���@�@�ݒu�E�ېݒu |
|||||
|
���l |
�@ |
||||
|
�����c�m�F�� |
�@ |
����t�� |
|||
|
�@ |
|||||
(��)
�{�ݍ\������
|
���h�����{�݂̍\���� |
�h�ΐ��� |
�ݒu�ꏊ�̈ʒu�ʁ@�@���H�E��n�E���ԏ� �\���@����ł��E���i�@�@�@�@�^���@�T�^�E�U�^�E�V�^ ���݁@�n�����E���n���� ��Չd�@(�@�@�@)t�^m 2 �@�@�@�@���k���x(�@�@�@)kg�^cm 2 |
||
|
�e�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m 3 �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m�~(�@�@)m �����X���u�܂ł̍����@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �z�Ǔ����E�̒��a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m ��݃s�b�g��ӂ̒����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m ��݃s�b�g�[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m |
||||
|
�S�̎�ށ@�@�@�@�@SD295�ESD345 �S�؏d�ʁ@�@�@(�@�@�@)kg�E�S�؊Ԋu�@(�@�@)cm �S���Ԃ����(�@�@�@)cm�E�O���@�@�@(�@�@)cm ���ʌ�(�@�@)cm�E�V��(�@�@)cm�E���(�@�@)cm �h�������^��(�@�@)mm�@�@�^���b�v�Ԋu�@(�@�@)cm |
||||
|
���i�̉�Ж� ���i�̔F��ԍ� |
||||
|
�̐����@�ݒu�E�ېݒu�@�@�n�Ֆʍ�(�@�@�@)m(�@�@)�ӏ� |
||||
|
���ΐ� |
�ݒu�ꏊ�̈ʒu�ʁ@�@�@�ԓ��E���� �{�b�N�X�̍\�� �W�̍\�� ��t�z�nj��a�@�@(�@�@�@)mm |
|||
|
�v�[�� |
�����nj��a�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)mm �z�Ǔ����E�̑傫���@�@�@��(�@�@)cm�~�c(�@�@)cm �̐����̐��� |
|||
|
���h�����p��n |
�i���H�����@(�@�@)m�@�@�@�@�@�@�@�ޏo�H�����@(�@�@)m ��n���猚�z���܂ł̋����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)m �n�Վx�����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�@�@)�g���d ��n�̍L���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����(�@�@)m�~��(�@�@)m |
|||
|
�����̎�� |
�@ |
|||
|
�s�s�v��̋��� |
(�@)�s�s�v��s�X����� (�@)�s�s�v��s�X��������� (�@)�s�s�v����O |
�p�r�n�� |
�@ |
|
|
�X��� |
�s�X�n�E���s�X�n |
|||
|
�p�n�A���y�ъǗ��ӔC |
(�@)���ȊǗ��@�\�� (�@)�y�n��t(���n)�\��@�@�@�@(�@)�{�݊�t(���n)�\�� |
|||
|
�v�ҏZ���E���� |
TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|||
|
�H�������ҏZ���E���� |
TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|||
���l�@1�@���̗p���̑傫���́A���{�H�ƋK�iA4�Ƃ���B
�@�@�@2�@�t�ߌ���}(2,500����1)�A�z�u�}�A�K�v�ɂ�蕽�ʐ}�A�\���}�A�z�ؐ}���̊W�}����Y�t���邱�ƁB
�@�@�@3�@���́A�L�����Ȃ����ƁB
(�\)
�J���s�ד��Ɋւ���R������
|
�{�s���̏ꏊ |
�@ |
||||||||
|
�J���s�ד��̖��� |
�@ |
�{�s���̖ʐ� |
m 2 |
||||||
|
�K�p |
���h�����{�� |
1�@3,000m 2 �ȏ� 2�@1,000m 2 �ȏ� �@3,000m 2 ���� |
40t���� |
�� |
|||||
|
20t���� |
�� |
||||||||
|
���ΐ� |
�� |
||||||||
|
���h�����p��n |
1�@3�K�ȏ�(�{�s���ʐ�1,000m 2 �ȏ�) 2�@3�K�ȏ�(���z�s��) |
||||||||
|
�K�p���O |
���h�����{�� |
1�@�L���ȏ��h�����ɂ���� �@�u�s�X�n�E���s�X�n�v �@�@�ߗ��ƒn��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�A���ƒn��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�B�H�ƒn��A�H�Ɛ�p�n��@�@�@�@�@���a100m�ȓ� �@�C��L�ȊO�̒n��@�@�@�@�@�@�@�@�@���a120m�ȓ� �@�u�s�X�n�E���s�X�n�ȊO�v �@�D���w��n��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a140m�ȓ� 2�@���z���̉����ʐς�100m 2 ���� |
|||||||
|
���h�����p��n |
1�@�ߕʕ\��1(5)�����œ�������m��(�����͏㉺���쎮) 2�@����6m�ȏ�̓��H�ɖʂ��A�L������͈͈ȓ� 3�@�ߕʕ\��1(5)�����ȊO��2�o�H�m�� |
||||||||
|
���h�����{�� |
�h�ΐ��� |
�`�� |
��w���A�L�W�L�ꎮ�̒n���� |
�@ |
|||||
|
���� |
�n�Ֆʉ��@4.5m�ȉ�(��݃s�b�g�����B) |
�@ |
|||||||
|
�搅���� |
���[�@0.5m�ȏ� |
�@ |
|||||||
|
�z�Ǔ����E |
�n�㍂1m�ȉ��Ń|���v�Ԃ̋z���\�Ȕ͈� |
�@ |
|||||||
|
20t�|1�@�@40t�E60t�|2�@�@100t�|3�ӏ��ȏ� �ی`�@���a60cm�ȏ�(�ʐ}��3) |
�@ |
||||||||
|
�������S�� |
�ʐ}��4 |
�@ |
|||||||
(��)
|
���h���� |
�h�ΐ��� |
�̐��� |
�n�Ֆʍ��@�@0.5m�ȏ�1m�ȉ� 20t�|1�@�@�@40t�E60t�|2�@�@�@100t�|3�ӏ��ȏ� |
�@ |
|
|
�W���E�W�� |
�ʐ}��1�@�@�ʐ}��2 |
�@ |
|||
|
��݃s�b�g |
�z�Ǔ����E�̐^���@�@��Ӗ��͒��a60cm�ȏ� �[��50cm�ȏ� |
�@ |
|||
|
�e�ʌv�Z |
��݃s�b�g�A�A�����ǁA�z�Ǔ����E�������B |
�@ |
|||
|
��ډd |
�T�^�̏ꍇ�@�@�@1t�^m 2 �U�E�V�^�̏ꍇ�@t�|14t�`t�|25�d |
�@ |
|||
|
���k���x |
20t�|180kg�^cm 2 �@40t�E60t�|240kg�^cm 2 �@���i�|300kg�^cm 2 |
�@ |
|||
|
�z�� |
�@SD295�@�@SD345�@�@�@�@���a13mm�ȏ�ٌ̈`�S�� |
�@ |
|||
|
�T�^�s�b�`40cm�ȉ� �@1,600kg�ȏ� |
�U�^�s�b�`30cm�ȉ� �@2,000kg�ȏ� |
�@ |
|||
|
780kg�ȏ�(20t) |
�@ |
||||
|
���Ԃ� |
����3cm�ȏ�@�@�O��5cm�ȏ� |
�@ |
|||
|
��̌� |
�T�^20cm�ȏ� |
�U�^25cm�ȏ� |
�@ |
||
|
�h�������^�� |
20mm�ȏ� |
�@ |
|||
|
�^���b�v |
35cm�Ԋu |
�@ |
|||
|
���p�� |
�����Ƀn���`��݂���ꍇ�̓n���`�ؔz�� |
�@ |
|||
|
���r�� |
�@ |
�@ |
|||
|
���ΐ� |
1�@�n���� |
�@ |
|||
|
2�@�P�����َ� |
�@ |
||||
|
3�@�X�p�t��(�X�p�̊p����2����3m�̈ʒu) |
�@ |
||||
|
4�@������̎ԓ��ɋ߂��ʒu |
�@ |
||||
|
5�@�H�[���炨���ނ�1m�̈ʒu |
�@ |
||||
|
�v�[�� |
1�@�z�Ǔ����E���͏��h�p�̐����ݒu |
�@ |
|||
|
2�@�����nj��a100mm�ȏ�@�@�z�ǐڑ�������a75mm |
�@ |
||||
|
3�@�z�Ǔ����E60cm�~60cm�ȏ� |
�@ |
||||
|
���h������n |
�W���E�W�� |
�ʐ}��5 |
�@ |
||
|
��ډd |
20t�ȏ� |
�@ |
|||
|
��n�ʐ� |
��6m�~12m |
�@ |
|||
|
�O�ǖʂ���̋����@�@�@�ʕ\��1 |
�@ |
||||
|
��� |
�x��ƂȂ�H�앨�� |
�@ |
|||
|
�i���H |
�ʕ\��2 |
�@ |
|||
|
���� |
(5)�����@�@�@�@�㉺���쎮 (5)�����ȊO�@�@2�o�H�m��(���ʊK�i���͔����) |
�@ |
|||
|
���l |
�@ |
||||
�@�@���c�����������Ƃ��m�F����B
�@
�@
�@�@�@�@�@�N�@�@���@�@���@�@�@�@�@���c��@�@�@�@�@��
�@�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{�����h��
|
���h�{�ݍH�������͏o�� �N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l �͏o�ҁ@�@�Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���L�̂Ƃ���A�J���s�ד��ɔ������h�{�݂̐ݒu�H�����������܂����̂œ͂��o�܂��B �L |
||||
|
�ݒu�� |
�Z�� |
�@ |
||
|
���� |
�@ |
|||
|
�{�s���̏ꏊ |
�@ |
|||
|
�{�s���̖��� |
�@ |
|||
|
���c�����y�єԍ� |
�@ |
|||
|
���h�{�݂̎�ށE�� |
�@ |
|||
|
�R���������� |
�@ |
|||
|
������������ |
�@ |
|||
|
���o�ߗ� |
�@ |
����t�� |
�@ |
|
���l
�@1�@���̗p���̑傫���́A���{�H�ƋK�iA4�Ƃ���B
�@2�@�t�ߌ���}�E�z�u�}�E�{�ݍ\���}�E�ʐ^��Y�t���邱�ƁB
�@3�@���́A�L�����Ȃ����ƁB
|
���h�{�݊��������� |
||
|
�ݒu�� |
�Z�� |
�@ |
|
���� |
�@ |
|
|
�{�s�ꏊ |
�@ |
|
|
���c�����y�єԍ� |
�@ |
|
|
���h�{�݂̎�� |
�@ |
|
|
�H�������������� |
�@ |
|
|
�o�ߑ[�u�y�ь������̈ӌ� |
||
|
���h�{�����Ϗ� ��@�@�@�@�@�� �N�@�@���@�@�� ���h���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���L�̏��h�{�݂́A�}���쑾�ɕ{���h�g�����h�{���J���s�ד��ɔ������h�{�݂Ɋւ���v�j�̋Z�p��̊�ɓK�����Ă��邱�Ƃ��ؖ�����B �L |
||||||
|
�@ |
�\���� |
�Z�� |
�@ |
�@ |
||
|
���� |
�@ |
|||||
|
�{�s�ꏊ |
�@ |
|||||
|
�{�s��於�� |
�@ |
|||||
|
�{�s�ʐ� |
�@ |
�p�r |
�@ |
|||
|
���h�{�݂̎�ޓ� |
���h�����{�݁@�@�@�@�@����a�@�@�@�@m �@�@�h�ΐ����@�@�@�@�@�\���@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�ʁ@�@�@�@�@�@�@�@�g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^���@�@�@�@�@�@�@�@�^ �@�@���ΐ��@�@�@�@�@���a�@�@�@mm�@�@�@�@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@mm�@�@�@�@�@�� |
|||||
|
���h�����p��n |
||||||
|
�����N���� |
�@ |
|||||
|
�������E���� |
�@ |
|||||
|
�@ |
||||||
|
���������s�����ו� |
||
|
�ݒu�� |
�Z�� |
�@ |
|
���� |
�@ |
|
|
�{�s�ꏊ |
�@ |
|
|
���c�����y�єԍ� |
�@ |
|
|
�s�����h�{�݂̎�� |
�@ |
|
|
�H�������������� |
�@ |
|
|
�o�ߑ[�u�y�ь������̈ӌ� |
||
|
�J�����O�R����ʕ� �N�@�@���@�@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�l �E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@ �@ �@ �@ �@�W�L�̂��Ƃɂ��āA���L�̂Ƃ���������܂��B �L |
|||
|
���O�R������� |
�@�@�@�@�@�N�@�@���@�@���@�@���@�@������@�@���@�@���܂� |
||
|
���O�R����ꏊ |
�@ |
||
|
�o�Ȏ� |
�@ |
||
|
�����n���� |
�@ |
�p�r |
�@ |
|
�{�s�ꏊ�E�ʐ� |
m 2 |
||
|
�{�� |
TEL�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
||
|
�v�ƎҖ� |
�S���ҁ@�@�@�@�@TEL�@�@�@�@�@�@�@�@ |
||
|
�{�s�ƎҖ� |
�S���ҁ@�@�@�@�@TEL�@�@�@�@�@�@�@�@ |
||
|
�����H���v�� |
�@�@�@�@�N�@�@�@�@�������H�@�@�@�@�N�@�@�@�@���������\�� |
||
|
�w������ |
|||
�J�����c�ԍ���
|
���c�N���� |
���c�ԍ� |
�J���ꏊ |
���̓� |
�\���� |
��t�� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�����ϔԍ���
|
�����N���� |
�����ԍ� |
���c�N���� |
���c�ԍ� |
�J���ꏊ�y�і��� |
�\���� |
���� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�N�@�@���@�@��
���c�ԍ��@��@�@�@�@�@��
���h�����{�ݏ��n(��t)���c��
�h�ΐ���
|
���ݒn |
�@ |
||
|
�n�� |
�n�� |
���L�� |
|
|
�@ |
�@ |
�@ |
|
���ΐ�
|
� |
���a |
�z�ǂ̒��� |
���L�� |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@�@�@�y�n
�@��L�̎{�݂��A���h�����{�݂Ƃ��Ė����ɂāA�@�@�@�@�@�@�@�s�ɏ��n(��t)���邱�Ƃ����܂��B
�@�Ȃ��A���c��͂��݂₩�Ɂ@�@�@�@�@�s�@�@�@�@�@�ۂƋ��c�����n(��t)�Ɋւ���葱���\�����������܂��B
�@�@���c�l�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@(���n��)�@�@�@�@�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�N�@�@���@�@���@�@
���c�ԍ��@��@�@�@�@�@���@�@
�@
���h�����{�݊Ǘ����c��
|
���ݒn |
�@ |
|
�{�ݖ� |
�@ |
|
�e�� |
�@ |
|
���a |
�@ |
|
� |
�@ |
|
�z�ǂ̒��� |
�@ |
�@��L�́A���h�����{�݂̊Ǘ��ɂ��ẮA���L���c�����̂Ƃ���Ǘ����܂��B
�L
1�@�R���A�������{�݂Ɉُ킪����ꍇ�́A�������ɉ��C�A���P�������܂��B
2�@�W�������V���������ꍇ�͉��P�������܂��B
3�@�w����h�����Ƃ��āA�펞�g�p�\�ȏ�Ԃňێ��A�Ǘ����܂��B
�@���c�l�@�@ �Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@(�Ǘ��ґ�)�@ �����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@(�W��)
�@(�W��)
�@(�z�Ǔ����E�W)
�@(�����������S��)
�@(���h�����p��n)